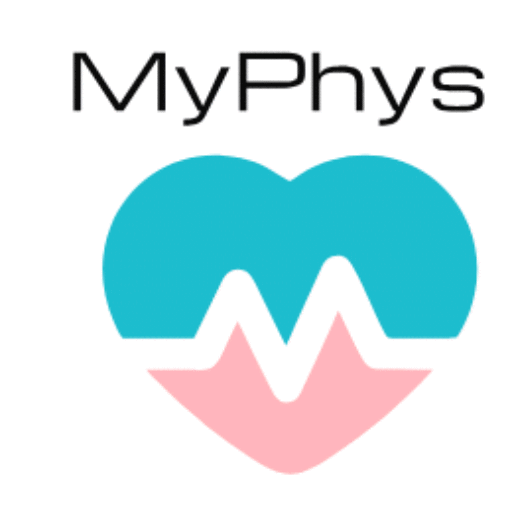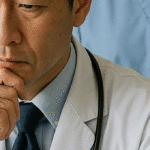肥満治療薬について
肥満治療薬は、 食事療法 や 運動療法 を行っても十分な効果が得られない場合や、肥満関連の健康リスクが高い場合に使用される医薬品です。
医師の指導のもとで処方され、適切に使用することで体重減少や健康状態の改善をサポートします。
肥満治療薬の種類
肥満治療薬は、大きく 食欲抑制薬、脂肪吸収抑制薬、代謝促進薬 の3つに分類されます。
1. 食欲抑制薬
- 脳の中枢神経に作用し、食欲を抑えることで摂取カロリーを減少させます。
- 満腹感を得やすくし、食事量のコントロールを助けます。
代表的な薬
- サノレックス(マジンドール)
- 日本で承認されている唯一の食欲抑制薬。
- BMI35以上の高度肥満者向け。
- 使用期間は最長3か月。
副作用
- 不眠、動悸、口渇、便秘、依存症のリスク
2. 脂肪吸収抑制薬
- 腸内での脂肪吸収を抑え、脂肪の一部を便として排出します。
- 食事由来の脂肪分を直接減らすため、脂質の多い食事を摂取する際に有効です。
代表的な薬
- ゼニカル(オルリスタット)
- 小腸や膵臓から分泌される消化酵素「リパーゼ」を阻害。
- 吸収される脂肪量を約30%減少させます。
副作用
- 油分の多い便、下痢、便失禁、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収低下
3. 代謝促進薬
- 脂肪の燃焼を促進し、エネルギー消費量を増加させます。
- 基礎代謝を高める作用があり、運動療法と併用するとより効果的です。
代表的な薬
- GLP-1受容体作動薬(セマグルチド・リラグルチド)
- 血糖値を調整するホルモンGLP-1を模倣し、満腹感を高めます。
- 糖尿病治療薬としても使用されます。
副作用
- 吐き気、嘔吐、腹痛、便秘
肥満治療薬の使用基準
肥満治療薬は、以下の基準を満たす場合に処方されることが一般的です。
- BMI30以上(高度肥満)
- BMI27以上 かつ 肥満関連疾患を有する場合
- 例:高血圧、脂質異常症、2型糖尿病、脂肪肝など
- 食事療法や運動療法を6か月以上継続しても効果がない場合
肥満治療薬の注意点
-
医師の指導のもとで使用
- 自己判断での服用は禁物です。副作用や相互作用のリスクがあるため、医師の指示に従いましょう。
-
生活習慣改善と併用
- 治療薬だけに頼らず、食事管理や運動も並行して行うことが重要です。
-
長期使用の注意
- 一部の薬は依存や耐性が形成される可能性があるため、使用期間に制限があります。
-
定期的な健康チェック
- 体重や血圧、血糖値などを定期的に測定し、薬の効果や副作用を評価します。
まとめ
肥満治療薬は、適切に使用することで体重管理や健康リスクの低減に役立つ有効な手段です。ただし、薬物療法は 生活習慣の改善 が基本となるため、無理のない範囲でバランスの取れた治療を続けることが重要です。疑問や不安があれば、医師や薬剤師に相談しながら、自分に合った方法を見つけていきましょう。